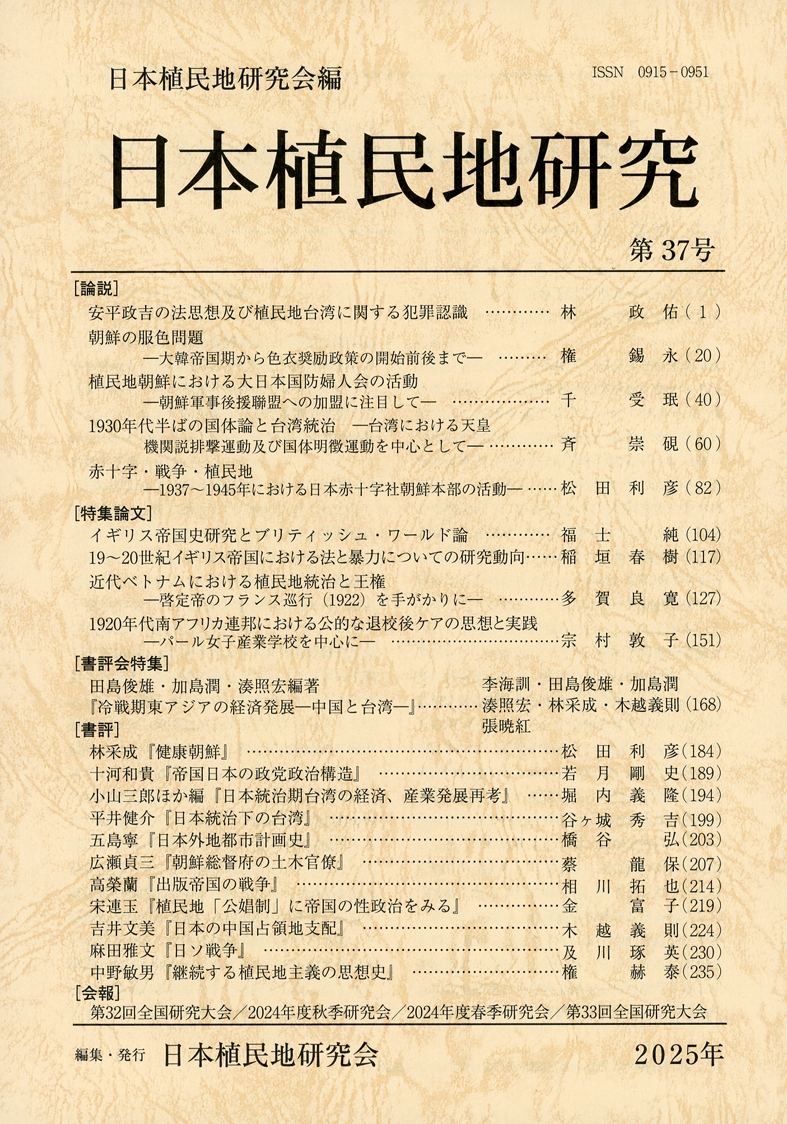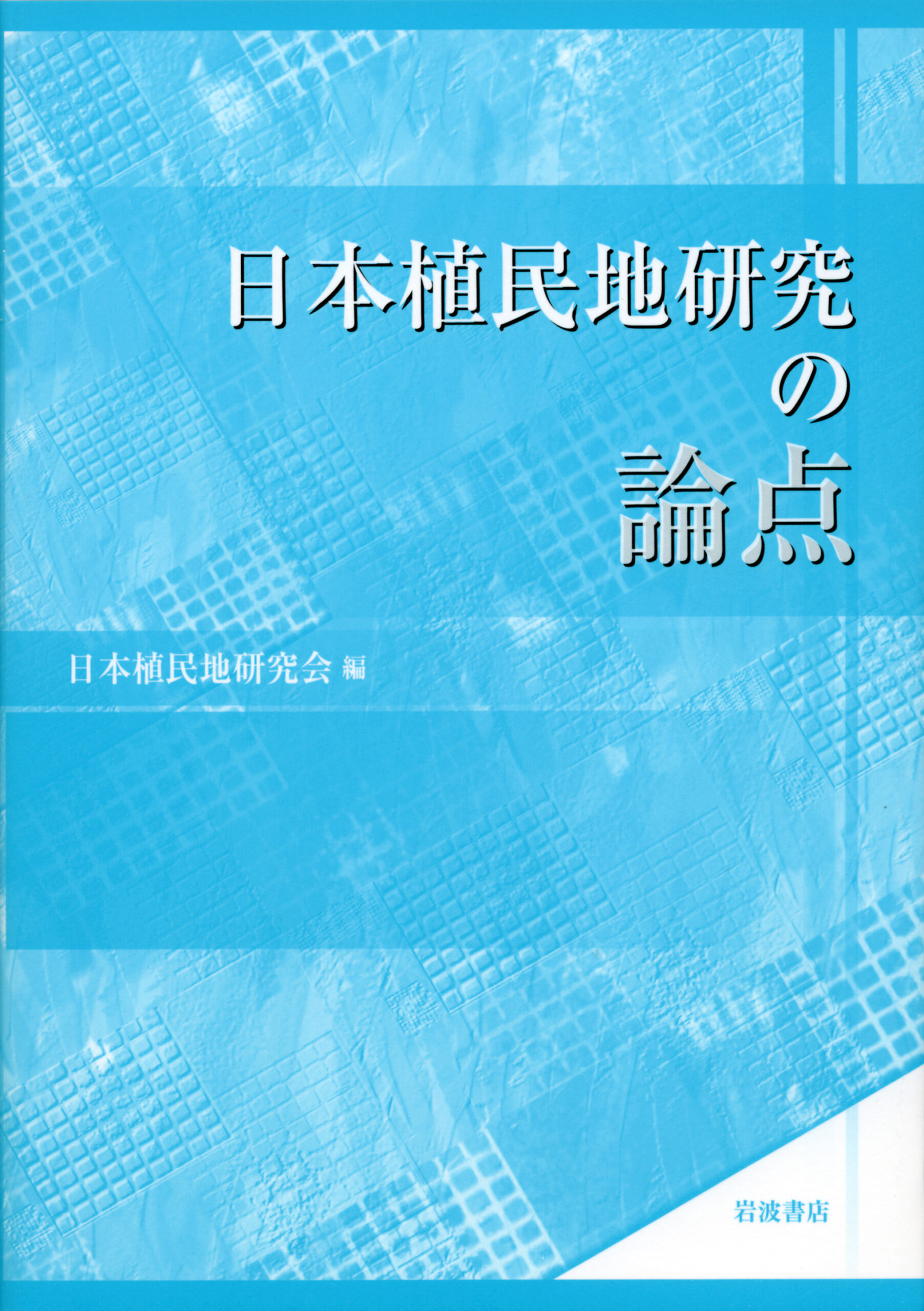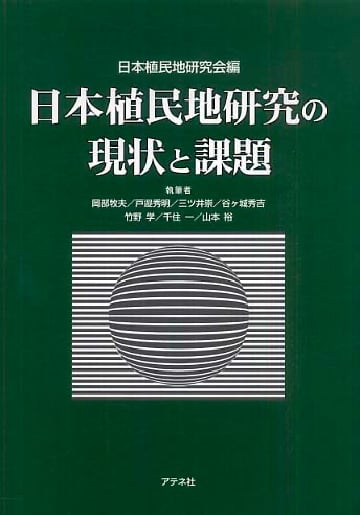日本植民地研究会について
当研究会について
代表理事あいさつ
新ホームページの開設に際しまして、当研究会の紹介と代表理事の挨拶を申し上げます。
1986年12月創立の日本植民地研究会は、東京周辺在住の月次例会に参加可能な研究者十数名による小規模な学会として始まりました。88年に年報『日本植民地研究』を創刊し、92年には全国組織化を果たし、2025年6月現在で会員数は179名となりました。現在は毎夏の全国研究大会と春季・秋季研究会を開催し、年報『日本植民地研究』も今秋で第37号を迎えます。これに加えて、創立20周年記念として、方法論と地域別研究の到達点を示した『日本植民地研究の現状と課題』(アテネ社、2008年)を、30周年記念として、より多様化する研究状況を22章と13コラムで構成した『日本植民地研究の論点』(岩波書店、2018年)を刊行しました。
個人的な見解の入るところですが、これまでの当研究会の研究潮流をまとめてみますと、創立当初より全面化されたのは、帝国主義研究の一環としての日本植民地の歴史研究でした。これは、日本帝国主義による侵略に問題意識を強く抱き、支配と被支配の「垂直的な関係」の実態を実証的に明らかにするものでした。これに対して寄せられたのは、そこからこぼれ落ちた、または、その陰に隠れた関係への問題関心でした。つまり、日本と植民地・占領地との「相互連関」「相互作用」を、学際的・分野横断的に、戦後・解放後・独立後にも接続して分析するものです。そして今、グローバル・ヒストリーなどが提示する総合的な歴史像をふまえて、日本以外の国々の植民地研究との比較・接続が展開されています。このような潮流は、世代間継承を内包した「研究蓄積」と学術的批判に裏付けられた「緊張感」に支えられており、ここに日本植民地研究会の特性のひとつがあるように思います。
このような特性の先に、新しい地平も感じています。侵略と支配をめぐる研究は、戦後・解放後・独立後のインタビューや証言のほか、画像・映像・音声・遺跡などの資料をデータサイエンスと接続することで、被支配側の人々の「痛覚」や「矜持」などをより詳らかにすることができるように思います。日本と植民地・占領地の相互連関・相互浸透をめぐっては、今日の政治・経済関係や文化交流の変化を反映して、「植民地的経路依存」をめぐる評価をアップデートすることが可能かもしれません。そして、各国の植民地・占領地研究との比較・接続は、学校教育現場との協同を通じて、当研究会の「プレゼンス」を再構築する活動になることが期待されます。
来年2026年には創立40周年を迎えます。ここに、会員の皆さまの変わらぬご支援をお願い申し上げるとともに、非会員・旧会員の皆さまの入会・再入会を心よりお待ち申し上げる次第です。
2025年10月
平山 勉
役員・幹事・監査委員(2025-26年度)
代表理事
平山勉
理 事
石川亮太、小野純子、加藤圭木、河西晃祐、小林信介、小林元裕、末永恵子、鈴木哲造、千住一、十河和貴、高江洲昌哉、竹野学、張暁紅、塚瀬進、中野良、平井健介、三木理史、谷ヶ城秀吉、山本裕、李海訓
事務局
事務局長:鈴木哲造
局員:大庭裕介(書記)、十河和貴
編集委員会
委員長:平井健介
委員:石川亮太、梅村卓、加藤圭木、兒玉州平、千住一、十河和貴、三木理史、湯山英子、吉井文美
研究企画委員会
委員長:小野純子
委員:秋田朝美、大岡響子、呉穎濤、小谷稔、小林信介、高江洲昌哉、竹野学、林英一、福井譲、宗村敦子、李海訓
広報委員会
委員長:河西晃祐
委員:通堂あゆみ、中野良、平井健介、平山勉、谷ヶ城秀吉、山本裕
ハラスメント 対策委員会
委員長:末永恵子
委員:慎蒼健、張小栄、辻原万規彦、李海訓
会計委員会
委員長:張暁紅
委員:鈴木哲造
監査委員
岡部桂史
会員数
179名(2025年6月現在)
沿 革
1986年12月
日本植民地研究会 設立
1988年12月
年報『日本植民地研究』を龍渓書舎より創刊
1991年6月
『日本植民地研究』(第4号)で初の特集(「日本の資本輸出」)
1992年9月
研究会の全国化にむけて130名に呼びかけ
1993年7月
第一回全国研究大会開催
代表委員・事務局長・編集長による運営体制に
『日本植民地研究』を自費出版(第5号のみ)
1994年6月
『日本植民地研究』を総和社より発売(第6~12号)
2001年6月
『日本植民地研究』をアテネ社より発売(第13号から現在まで)
2008年6月
創立20周年記念として、『日本植民地研究の現状と課題』(アテネ社)を刊行
2009年1月
旧ホームページ開設
2011年6月
代表委員を代表理事に名称変更
理事会・研究企画委員会を設置
2016年11月
春季/秋季研究会の地方開催を開始(立命館大学)
2018年7月
創立30周年記念として、『日本植民地研究の論点』(岩波書店)を刊行
全国研究大会の地方開催を開始(北海学園大学)
2024年7月
広報委員会・会計委員会を設置
2025年7月
ハラスメント対策委員会を設置
2025年10月
新ホームページ開設
会 則
日本植民地研究会会則(2025年7月19日一部改正)
第1条 本会は、日本植民地研究会と称する。
第2条 本会は、日本植民地問題に関する研究を進め、会員間の交流を目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 年1回の研究大会および会員総会の開催
② 定例研究会の開催
③ 年報『日本植民地研究』の発行
④ その他、本会の目的を達成するために必要な諸事業
第4条 本会の目的に賛同し会則にしたがう者は、国籍その他を問わず、本会の会員となることができる。
2 本会の会員になることを希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記入して事務局に届け出るものとする。
3 会員は、研究大会および定例研究会に出席し、研究報告を行うことができる。また、年報に投稿し、年報の配布を受けることができる。
4 会員は、会員総会に出席し、本会の役員となることができる。
5 会員は、会費として年額4,000円を納入するものとする。会費3年度分以上の未納者は、特別の事情がないかぎり、退会したものとみなす。
第5条 本会の最高決定機関は、会員総会である。
2 すべての会員は、会員総会に出席し、意見を述べ、議決に加わることができる。
第6条 会員総会は、毎年1回代表理事が召集する。
第7条 会員総会において、会員中から役員を選任する。役員は、代表理事1名、理事20名以内および監査委員1名とする。
2 代表理事は、本会を代表し、理事会を主宰して会としての意思を決定することができる。
3 理事は、理事会を構成して会務を執行する。代表理事に事故あるときはその職務を代行する。
4 理事会は、理事に選出された会員中から事務局長、会計委員長、編集委員長、研究企画委員長、広報委員長、ハラスメント対策委員長各1名を選出する。
5 事務局長は、事務局員若干名とともに事務局を組織し、会員総会の運営と会員の連絡にあたる。
6 会計委員長は、会計委員若干名とともに会計委員会を組織し、会計業務にあたる。
7 編集委員長は、編集委員若干名とともに編集委員会を組織し、年報の編集・発行にあたる。
8 研究企画委員長は、研究企画委員若干名とともに研究企画委員会を組織し、研究大会・定例研究会の運営にあたる。
9 広報委員長は、広報委員若干名とともに広報委員会を組織し、広報活動およびホームページの管理等を行う。
10 ハラスメント対策委員長は、ハラスメント対策委員若干名とともにハラスメント対策委員会を組織し、ハラスメントの防止・対策に関する業務にあたる。
11 監査委員は、本会の会計および資産を監査し、会員総会において監査報告を行う。
12 事務局員・会計委員・編集委員・研究企画委員および広報委員(以下、幹事とする。)は、代表理事が委嘱する。
13 代表理事は、監査委員及び幹事を理事会にオブザーバーとして出席させることができる。
第8条 前条の役員・委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第9条 本会の会計年度は、当年7月から翌年6月までとする。
2 会計委員長は、会計決算報告書を作成し、理事会の承認を経て年次総会に提出する。但し、会計決算報告書は会計監査を経てから理事会に提出しなければならない。
第10 条 本会の事務局は、理事会が定める場所に置く。
2 必要に応じて地方部会を設けることができる。
第11条 この会則の改正は、会員総会の承認を必要とする。
付則 この会則は、1994年6月5日より発効する。
2002年6月23日一部改正
2004年7月4日一部改正
2005年7月3日一部改正
2011年7月3日一部改正
2016年7月3日一部改正
2018年7月15日一部改正
2024年7月20日一部改正
2025年7月19日一部改正